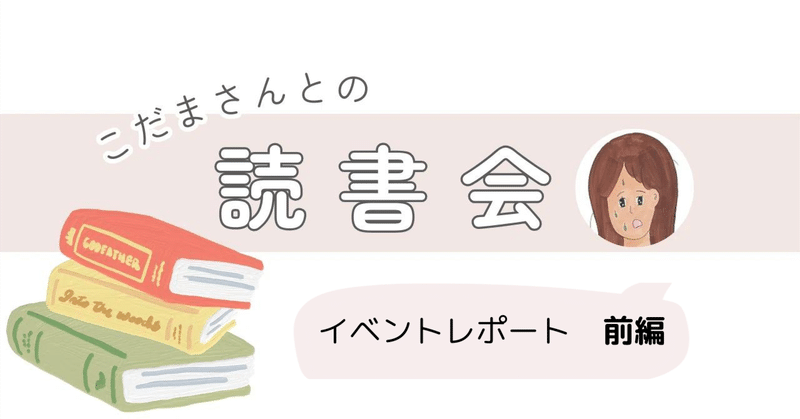
イベントレポート「こだまさんとの読書会」前編
4月26日(金)、イベント「こだまさんとの読書会」を行いました!
お待たせいたしました、とてもとても遅くなってしまい恐縮です。あったこと、感動したこと全部を書き切らねば!みたいに気負いすぎてまったく着手できず…。
そんなんしてたら一生なにもできないので、ライトにいこう、ライトに…という姿勢で向き合ったところ、ようやく書き進められました。以下、イベント当日のレポートです。
みんなが緊張している
19時半過ぎ。こだまさん、ハリ書房さん、そして6人の参加者の方々が全員集合し、待ちに待ったイベントスタート。
至近距離での対面に緊張した面持ちの皆さん。リラックスを促す私も、スムーズな進行ができるかどうか緊張でいっぱい。そのことを正直に話すと「私が一番緊張していると思います!」とこだまさん。
この場にいるみんなが緊張している…。そう思うと少しホッとして、たどたどしいながらイベントの流れを説明し、まずは自己紹介から始めました。
過去に別の場所で開催されたこだまさんのイベントにも参加したことのある方、こだまさんとSNSでつながりのあった方、そしてこのイベントのためにはるばる関西地方からお越しになられた方(!)まで。皆さん、こだまさんのことが本当に好きなのだと実感しました。
イベントの流れ
ざっくり、イベントの流れは以下のように設定しました。
・こだまさんへのプチインタビュー(約20分。聞き手:いりえ店主)
・参加者の方々のお話(持ち時間1人あたり約8分)
・時間が残れば質疑応答
1時間半という限られた時間だったので、プチインタビューが20分くらいだとして、念のため予備の時間も考えると1人あたりの持ち時間は非常に微妙な約8分、という計算になりました。
ひたすらにこだまさん
さて、まずはプチインタビューから。これは店主が個人的にお訊きしてみたかったことについて自由に質問させていただくという贅沢かつ自分よがりなコーナーでした。以下、Q&A形式(+補足説明)でご紹介。
Q(店主):こだまさんは『覚醒するシスターフッド』(河出書房新社)で短編小説を書かれています。まずは経緯を教えていただけますか?
※補足説明:同書でこだまさんは「桃子さんのいる夏」という短編小説を書かれています。とある田舎の村に移住体験でやってきた都会的な桃子さんとその夫。そして一度は地方都市に出たものの、小学校の教員として村へ戻ってきた美沙が主要登場人物です。
A(こだまさん):『文藝』の編集者さんから小説を書いてみませんか?と打診があったのですが、最初は「できない」と思いました。でもきっと最終的には書きたかった。「女性同士の連帯について書いてほしい」とテーマもいただいたので、テーマがあれば書きやすいかなと思ってお受けしました。
あと、自分はあちこちで「小説は書けません」と散々言ってきたのですが、ある方から「こだまさんの文章は小説っぽいですね」と言われたことがあり、普段のまま書いてみようと思いました。
Q:私小説である『夫のちんぽが入らない』(扶桑社/以下、「おとちん」)以外で小説を書くのはほぼ初めてとのことでしたが、作品の着想はどこから得たのでしょうか。
A:創作は苦手なので、実体験を入れました。モデルになる人がいて、モデルになる場所があって、作中の「桃子さん」にあたる人とも出会っていて、その人のことを書きたいなと思ったんです。
実際にご夫婦で田舎にやってきて、そのときはすごく浮いていた。ご夫婦の描写は、男女平等な関係性もそうですし、生い立ちもほぼ現実と一緒です。ちょっと嘘を盛り込んだエッセイという感じで。モデルがないと書けないなと思います。
小説は、一部の崇高な人しか書けない、私が書くもんじゃないとずっと思っていたのですが、書き上げてみて、やっと少し「自分にも書けるのかな」と思えました。ただ、人称の使い方が難しかったり、小説の文体というものがまだまだ苦手。一から学ぶような気持ちで書きました。
Q:好きな作家さんや、小説を書く上で参考にされた作家さんはいますか?
A:今村夏子さんと高瀬隼子さん。やわらかいようで毒があったり、人間の奥深くを描くような文章が好きです。
Q:これからも創作はされたいですか?
A:4~5年前から「おとちん」の担当編集者の方がずっと待ってくださっていて、「けんちゃん」について書きたいと思っています。
小説を書くために自分でいろいろとやっているのは、舞台になりそうな地域の新聞をスクラップして集めています。発達障害のある子のお母さんについて取り上げた記事とか、あとは過疎地域の現状とか自然現象についての記事などをよくスクラップしています。
※補足説明:「けんちゃん」は、こだまさんが過去に勤めていた障害者施設に通うダウン症の少年。これまでにブログやエッセイなどでたびたび登場しています。
Q:次はエッセイの書き方について少し伺いたいです。こだまさんの文章における場面の描写はとても詳細だと感じます。また、ときに単調に感じられてしまいがちな風景描写がとても印象的で読みやすく、眼前に絵が浮かんできます。普段、こうした記憶の整理の仕方はどのようにしていますか?
A:面倒くさがりで日記は続かないので、おかしなことがあるとよくスマホにメモしておきます。情景とか、そのときの湿度といった自然のことなども記録したりします。あとはなんでもない写真を撮っておくこと。路地の写真とかを撮っておいて、後で見返したときに「ここに照明があったな」とか思い返します。
自分自身が風景描写をあまり集中して読めないたちなので、どうやったら読みやすくなるだろうというのは工夫しています。
Q:こだまさんの作品を読んでいると、自分の身に起こったことをどこか俯瞰して書いているように感じるのですが、こうしたメタな視点を持つコツはなんだと思われますか?
A:全然メタじゃないです。先日、吉村萬壱さんと対談したときに「本当のことを書くのがいい」というようなことを仰っていました。自分の実体験の、言える範囲の狭いことを書いているという感じです。
「おとちん」もすごく個人的なことを書いたのですが、自分に置き換えて読んでくださる方が結構いらして驚きました。
***
もう少し掘り下げてお訊きしてみたかったのですが、当初お伝えしていた設問にはすべて触れた+時間の関係上、プチインタビューはこの辺で打ち切ることに。
こだまさんは、ものすごく個人的なこと、それも性にまつわる話や恥ずかしかった話、やらかした話をとても冷静な筆致で淡々と書かれており、私はかなりメタ的な視点だなと感じていたため、最後のご回答は意外なものでした。
イベント終了後、参加者のお一人からも「こだまさんがご自身のメタな描写を全く自覚していなかったところ、すごく勉強になったと言うか、こだまさんのこだまさんたる所以みたいなものを感じられてとても良かったです」とのご感想をいただいて、ああそうか、こだまさんはひたすらに「こだまさん」なんだなあ…!と嘆息しました。
***
結構な長文になってしまったため、ここまでを前編とし、以降のパート(参加者たちのお話)はまた追ってアップいたします。引き続きどうぞよろしくお願いいたします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
